第29回 老人のパラドックス
公開日:2020年2月 7日 09時00分
更新日:2023年8月21日 12時56分
井口 昭久(いぐち あきひさ)
愛知淑徳大学健康医療科学部教授
人が成人に達してからずっと同じ運命がつづくことなどあり得ないのは明らかで、熟年に達すると人は老人に特有のパラドックスに直面する。
それは正から負、あるいは負から正への移行と呼べるものである。
正の移行が起きれば高齢者はより大きな知恵とより大きな学識を持つことになる(ハーヴェイ・C・リーマン)。
私は生涯を通じて食欲が沸かない人間であった。
美味しいという感覚を実感する機会が少ない、かわいそうな幼少期を過ごしたためである。
成人になってからは隙あれば酒を飲む機会を狙った生活をしていたためでもあった。
毎日が二日酔いで食事を楽しむ気分になれなかったのだ。
暑い夏の時期には食欲不振に悩んだものだ。
食欲不振をさらに深刻にしたのは食道がんの化学療法による副作用であった。
闘病中の苦い記憶は今でも鮮明に蘇る。
―7年前:病院入院中―
私は末期の食道がんと診断されて化学療法を受けていた。
病院の朝は早い。6時には目が覚めた。
病室を出て看護師詰め所で体重測定をした。食事量がめっきり減ってしまったので体重が減るのが心配でしょうがなかった。
それからエレベーターに乗って1階にあるコンビニへ新聞を買いに行くのが日課であった。
コンビニで新鮮そうに見えるサンドウィッチや"ふりかけ"を買った。
病院で出される朝食が苦手になっていたのだ。
私はその病院の病院長を過去に3年間勤めていたことがあった。
だから病院食の味には責任があったのだが、病院食は化学療法の副作用である食欲不振を覆すほどには美味しくはなかった。
病室に戻るとお茶が配られてきた。朝食の前触れである。
朝食はパンに卵に牛乳であった。
私はほとんど手をつけることなく呆然としていると、30分後ぐらいに下膳のおじさんが来る。申し訳ないと思いながらほとんど食べていないお膳を返す。
それから看護師の回診がある。体温を測定して血圧をはかり、酸素飽和度を測定する。
そして悪魔のささやきだ。「食事はどれだけ食べました?」「ほとんど食べれませんでした」と答えると、悲しい表情になる若い看護師がいた。
看護師に悲しい顔をされるほど困ることはないと、患者になって初めて知った。
患者は看護師の悲しい顔を見ると更に切なくなるのだ。
ようやく朝の行事が終了したところへ昼食が配られてきた。
「何故に人は一日に3回も食事をとらねばならぬのか」と思ったものだ。
「どの程度食べましたか?」「10%ぐらいです」「主食は?」「ご飯はほとんど食べれませんでした」そんな会話が来る日も来る日も続くのだ。
「空腹にまずい物なし」というが、空腹であるのにまずい物ばかりであった。
食物を口に入れて飲み込むまでの間に不快な物質に変質していき飲み込めなくなった。
拒食症まがいの患者にとって食事は拷問に似ていた。
放射線と化学療法を半年ほど続けると私の食道がんは消えた。
化学療法が終わると私は大きな転換が訪れた。
食欲が出てきた。
転換のもう一つの要因は酒からの脱却であった。
病気の性質から私は禁酒を余儀なくされることになった。
酒を飲まなくなると空腹でなくても旨い物を食べたくなったのだ。
美味しい食事を希求するようになった。
最近では新しい料理に挑戦するようになった。
ネットのレシピを印刷してスーパーへ行く。
食材を買って帰って工夫する。
私にハーヴェイのいう負から正への転換が起きたのだ。
私は老年になって今までなかったより大きな知恵と、より大きな学識を持つことになった。

(イラスト:茶畑和也)
著者
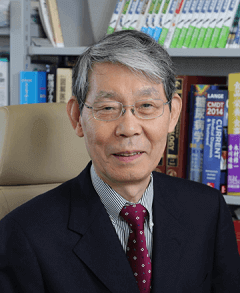
井口 昭久(いぐち あきひさ)
愛知淑徳大学健康医療科学部教授
1943年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2007年より現職。名古屋大学名誉教授。
著書
「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中でードクター井口の人生いろいろ」「誰も老人を経験していない―ドクター井口のひとりごと」(いずれも風媒社)など
