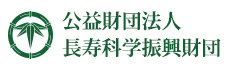高齢者のデジタルデバイド解消に向けたテクノロジーの可能性
公開日:2025年4月11日 10時30分
更新日:2025年4月11日 10時30分
加山 博規(かやま ひろき)
Google, Research & Core Partnerships 日本リード
このたびは、本誌『Aging&Health』への執筆の機会をいただき、誠にありがとうございます。本稿では、「高齢者のデジタルデバイド解消に向けたテクノロジーの可能性」というテーマで、弊社Googleの取り組みをご紹介させていただきます。
超高齢社会におけるデジタルデバイドの現状
皆様ご承知のとおり、日本は世界に先駆けて超高齢社会に突入し、厚生労働省の統計では、2030年には約3人に1人が65歳以上の高齢者になると予測されています。内閣府の国際比較調査によれば、日本の60歳以上の方の40%以上が今後も収入の伴う仕事をしたいと考えているというニーズも示唆されています。一方で、デジタル技術の急速な進展により、情報の入手、コミュニケーション、各種サービス利用など、生活のあらゆる場面でデジタル化が進んでいます。この変化は、高齢者にとって大きな挑戦となり得ます。新たなデジタル技術に馴染みのない方には、必要な情報やサービスにアクセスできなかったり、社会との接点が減少したりすることで、孤立や不便を感じる可能性が高まります。このテクノロジーの発展により生じた、いわゆる「デジタルデバイド」ですが、テクノロジーにはそれを解決できる可能性を秘めていると考えます。
Googleのミッション
Googleは、「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスして使えるようにすること」を世界共通のミッションに掲げ、創業以来、テクノロジーを通じて社会の問題解決を目指してまいりました。そして、不公平なバイアスの発生や助長を防ぐことをAI指針の一つとし、各国・地域の状況や課題に寄り添い、地域の方々と共に解決に取り組むことを重視しています。
ここ日本では、「AIの力で解き放とう、日本の可能性」を日本としてのミッションとして掲げ、高齢化をはじめとする様々な社会課題の解決に貢献したいと考えています。特に、高齢者の皆様の生活や社会参加をデジタルの力で支援し、心身両面での健康を支えるためにテクノロジーの活用を推進できればと取り組んでいます。それにより、高齢者ご自身の生活の質の向上と、経済成長の原動力として社会参加ができるお手伝いができると考えています。
Googleの最新技術とその可能性
Googleでは、Google検索、Googleマップ、Gmail、YouTube、Google Pixelなど、世界中で使っていただいているサービスを提供しています。これらのサービスや関連する技術は、高齢者の方にも有用な価値を届けられると信じています。例えば、Google検索やカメラ機能による、病気や健康に関する情報の入手。Googleマップによる、外出時の道案内だけでなく、近隣の病院や施設の検索・予約の簡便化。また、YouTubeでは、健康体操や趣味の動画など、高齢者の疾病予防をサポートしたり、生活を豊かにするコンテンツを提供することが可能だと考えています。
さらに、Googleは人工知能(AI)などの最先端技術の研究開発にも注力しています。例えば、これまでの生活習慣から健康に良い運動や食事の提案や、音声技術による日常生活のサポート、画像技術による、視覚障がいのある高齢者が周囲の状況をよりクリアに理解する手助けなど、まるで家族や友人のように日々の生活のお手伝いができる可能性を秘めていると考えられます。
日本における取り組み、社会貢献の事例:長寿科学振興財団との連携
しかし、これらの技術を実際に実現させること、そして安心安全にお使いいただけるように高齢者の方々に届けることは、Google個社だけでは困難です。そこで、私たちは、大学や研究所、医療機関などの、同じ問題意識を持つ専門家の方々との連携を重視しています。
その取り組みの一つとして、2022年に、Googleの非営利団体への支援を行うGoogle.orgから、長寿科学振興財団へ助成をさせていただきました。長寿科学振興財団は、「長生きを喜べる長寿社会実現研究支援」というテーマのもと、高齢者研究への深い知見と経験に基づき、学術的な効果検証に加え、社会実装の実現性にも着眼した取り組みをされています。この活動は、デジタル・AIの価値を日本全体に届けたい Googleのビジョンと強く共鳴するものです。
採択されたプロジェクトでは、高齢者を対象としたデジタルスキルプログラムが実施されました。高齢者が実際にデジタルツールを使いこなし、その利便性を実感することで、デジタルデバイドの解消につながることを期待しています。
産官学の連携と専門家による検証の重要性
高齢者へのデジタル技術普及においては、産官学の連携が不可欠です。企業が持つ最新技術やサービス、行政の持つネットワーク、そして大学や研究機関の持つ専門知識を組み合わせることで、より効果的かつ持続可能な取り組みを実現できると考えます。
特に、日本においては、社会課題を解決すべく取り組まれている高齢者の心理や行動特性を熟知した専門家や研究機関、そしてその高齢者の方をサポートする行政ネットワークも豊富です。それらの強みや知見を活かし、日本の高齢者と社会構造に最適応するような技術開発やプログラム設計を行うことが重要です。また、実際の効果を検証する研究も不可欠です。効果検証に基づき、プログラムを改善し、より多くの高齢者にとって使いやすく、拡張性があり、効果的なデジタル技術の提供につなげていく必要があります。
高齢者の方々にわかりやすく、使いやすい形でテクノロジーを届けるためには、単なる技術の提供だけでなく、丁寧なサポートや教育が必要です。地域コミュニティやボランティアの協力も得ながら、高齢者一人ひとりに寄り添った支援体制を構築していくことも重要だと考えます。
将来の超高齢社会におけるテクノロジーの役割
テクノロジーは、高齢者の生活をより豊かにし、社会とのつながりを維持するための強力なツールとなり得ます。遠隔医療、見守りサービス、オンライン学習、趣味や社会参加を支援するプラットフォームなど、テクノロジーの活用は、高齢者が年齢に関係なく、自分らしく生き生きと暮らす社会を実現する鍵となるでしょう。
Googleは、これからもAIをはじめとした技術革新を通じて、日本の超高齢社会における課題解決に貢献してまいります。そして、長寿科学振興財団をはじめとするパートナーの皆様と連携し、デジタルの力で日本の高齢社会の可能性を大きく花開かせられればと強く願っております。
本稿が、読者の皆様にとって、高齢者のデジタルデバイド解消とテクノロジーの可能性について考えるきっかけとなれば幸いです。
筆者

- 加山 博規(かやま ひろき)
- Google, Research & Core Partnerships 日本リード
- 略歴
- 京都大学大学院医学研究科修士号取得後、アマゾンジャパン合同会社入社。マーケティングマネージャー、その後、プロダクトマネージャーとして、新規顧客獲得やFire TVなどの機能企画開発をリード。その後、Googleに入社、医療AIの事業開発担当として、乳がんAIや新型コロナ感染者予測モデル開発などに従事。現在は、Google ResearchやGoogle DeepMindのパートナーシップ日本リードとして、特に健康・環境・少子高齢化などに注力し、日本の社会問題へのAI活用を推進している。
WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート
WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。
お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。