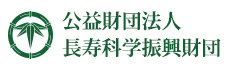高齢者のスマートフォン利用促進を介したアクティブライフ・コミュニティーの形成
公開日:2025年4月11日 10時30分
更新日:2025年4月11日 10時30分
島田 裕之(しまだ ひろゆき)
国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センターセンター長
山口 亨、山際大樹、赤井田将真、片山 脩
国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部
はじめに
スマートフォン(以下、スマホ)の普及等をはじめとして社会のデジタル化が進展し、ネットワークの高度化等も背景に、国民生活や経済活動における情報通信の果たす役割が増大している1)。デジタルは、地域社会の生産性や利便性を飛躍的に高め、産業や生活の質を大きく向上させ、地域の魅力を高める力を持っている1)。高齢者のスマホ保有率は60歳代で93%、70歳代で79%といった報告2)がある一方、70歳代以上のスマホやタブレットの利用率は48.4%に留まっており3)、高齢者の利用率向上の課題が残っている。スマホを利用しない理由には「自分の生活には必要ないから」、「使い方がわからないから」といった意見があがった3)。高齢者のスマホの利用率を高めるためには、多世代型の地域コミュニティーを創出し、地域の人材によるスマホの使い方等の適切な情報提供や技術講習の実施が重要である。
そこで、本プロジェクトではスマホのアプリケーションを活用した高齢者の活動性向上を支援するアクティブライフ・コミュニティーの形成に向けて、高齢者のスマホ利用促進を行う地域ボランティア(以下、デジタルヘルス推進員)を養成し、スマホのアプリケーション利用による高齢者の健康寿命延伸に対する効果を検討した。
本プロジェクトの成果目標
本プロジェクトでは、Google.orgから以下の5つの成果目標が設定された。
1)50の市区町村に100の地域コミュニティーを創出、2)当該コミュニティーに参加して若者とデジタルスキルを学習する高齢者が4,500人、3)当該コミュニティーに最低6か月間参加し続ける高齢者が全体の13%(600人)以上、4)当該コミュニティーが有益でありデジタルスキルに対する自信がついたと報告する高齢者が全体の70%、5)プログラム参加後に幸福度/生活の質が改善したと報告する高齢者が全体の60%であった。
「オンライン通いの場アプリ」
本プロジェクトでは、国立長寿医療研究センター(以下、当センター)が開発し無料公開したオンライン通いの場アプリ(以下、通いの場アプリ)を使用した4)。通いの場アプリは、身体活動、社会活動、知的活動を複合的に行えるだけでなく、日々の活動記録を自己管理することや友人、家族と活動記録を共有することが可能である。通いの場アプリの利用を通して、高齢者の活動性およびデジタルスキルの向上を図った。
成果目標 1)50の市区町村に100の地域コミュニティーを創出
1年目では、自治体との連携基盤を構築するため、デジタルヘルス推進員の養成と通いの場アプリの普及を中心とした研究協定を複数自治体との間で締結した。これらの自治体において、高齢者のデジタルスキル学習をサポートするデジタルヘルス推進員を養成し、地域に根差した通いの場アプリの普及やスマホ教室等の展開を開始した。養成研修会に向けて、電源を入れるなどのスマホの基本的な操作マニュアルやカメラの使用方法などの応用的な操作マニュアルを作成し、利用した。当センターから各自治体に講師を派遣し、自治体ではデジタルヘルス推進員となる参加者の募集と研修会会場の確保を行うことで、両者協働でデジタルヘルス推進員の養成を実施した。養成研修会では、受講者が実際にスマホを操作しながらサポートに必要なポイントを学習してもらった。
2年目には、活動地域をさらに拡張してデジタルヘルス推進員の養成を継続する一方、デジタルヘルス推進員らがさまざまな地域で通いの場アプリの利用を中心としたスマホ教室を展開した。
これらの取り組みは、地域コミュニティーの創出に大きく貢献した。2年間のプロジェクトで、デジタルヘルス推進員養成人数は216人となり、デジタルヘルス推進員を中心とした地域活動により64の市区町村で138の地域コミュニティーの創出が行われた。
成果目標 2)コミュニティーに参加し若者とデジタルスキルを学習する高齢者が4,500人
1年目から2年目にかけては、通いの場アプリの普及を促進するため、通いの場アプリの紹介チラシや操作マニュアル、さらには紹介用ホームページ、説明動画を作成して無料公開することで、自治体が手軽に通いの場アプリを導入できる体制を整備した。また、高齢者自身が健康や活動の自己管理を積極的に行えるようにするため、これらの作成媒体に加え、ケーブルテレビや新聞での広告を用いて通いの場アプリの普及に向けた対策を実施した。デジタルヘルス推進員は自治体と協働し、地域団体やサロン、公民館などで通いの場アプリをコンテンツとしたスマホ教室の展開を行い、誰にでもわかりやすく興味を抱かせるような工夫を行った。そうした活動の結果、全国の複数自治体から通いの場アプリの利用・普及希望の問い合わせを受け、当センターではWebミーティングを用いたデジタルヘルス推進員の養成研修会を開催するなどして、通いの場アプリの全国展開を促進し、高齢者のデジタルデバイドの解消と活動性の維持・向上に広く貢献した。
さらに、民間企業にも協力を依頼し、通いの場アプリの普及活動を支援する体制を整備した。これにより、デジタルヘルス推進員が実施したスマホ教室のフォローアップ教室を企業に開催してもらうなどの継続的な支援体制も構築した。一部の自治体では、若者の参入として地元の高校生に協力を依頼し、デジタルヘルス推進員の養成課程からサポート可能な体制を構築した(図)。

2年間をかけて実施した上記の活動により、通いの場アプリを中心としたデジタルスキル学習への参加人数は5,073人となった。
成果目標 3)コミュニティーに最低6か月間参加し続ける高齢者が600人以上
創出したコミュニティーへの参加を通して継続的なデジタルへのつながりが心身機能に対しどのような効果もたらすかを検証するため、教室型の介入プログラムを実施した。参加者は、およそ2,000人の地域高齢者を対象とするコホート調査から、教室型コミュニティーへの参加同意が得られ、継続参加に支障を来す可能性のある進行性疾患等を持たない652人をリクルートした。
1年目では、これらの参加者に対する介入前評価として、認知機能や運動機能の評価、生活習慣や精神心理状態の聴取、血液検査などを実施し、教室型コミュニティー介入を開始した。一部の参加者は元々スマホを所有していない方もおり、コミュニティーにはデジタルスキルのサポート役としてのデジタルヘルス推進員を配置することによって参加者の不安の軽減を図った。また、介入の効果を最大化するためのさまざまなアドヒアランス向上の取り組みを実施した。例えば、「毎日通いの場アプリを開くこと」、「毎日通いの場アプリの機能を使うこと」など参加者の生活に合わせた目標設定を行い、その目標を達成することができた場合にはインセンティブの付与を行った。また通いの場アプリに対する抵抗感を軽減するため、参加者から通いの場アプリに対する意見を聴取し、わかりやすく操作しやすいようにユーザーインターフェイスやユーザーエクスペリエンスの改善を複数回にわたり行った。
介入試験では脱落率が15%程度を見越して参加者数が設定されることが多いが、さまざまな取り組みにより本介入における教室型コミュニティーから脱落する参加者を最小限に抑えることができ、652人の参加者のうち、介入後評価まで完遂した参加者は611名(93.7%)であった。600人以上の高齢者がコミュニティーに6か月間参加し続けることができた。
成果目標 4)コミュニティー参加後にデジタルスキルに自信がついたと70%が報告
本プロジェクトでは、教室型コミュニティーの創出を行い、そのコミュニティー内でデジタルスキルを学習するという介入を実施した。介入では通いの場アプリを主なツールとして611名の高齢者がデジタルスキルを学習し続けた。参加者は60代から80代の男女であり、611名の参加者のうち196名(32.1%)が本介入プログラムによりスマホを貸与され、デジタルとのつながりを促進することとなった。196名の参加者の中には本介入プログラムをきっかけに介入中、あるいは介入後に自身でスマホを購入・所有することにつながったケースも見られた。
介入プログラム終了後に実施した介入後評価において、「デジタルスキルに自信がついたか」を評価した結果、611名のうち358名(58.6%)が介入プログラム前に比べ自信がついたと回答した。年齢や性別、本介入プログラムによりスマホを貸与されたか否かという要因別にも詳細に解析を行った。その結果、本介入プログラムをきっかけにスマホを貸与された75歳以上の後期高齢女性において、デジタルスキルに対する自信がついた者が最も多かった(72.5%)。一方、元々スマホを所有している参加者や男性においては本介入プログラムにてデジタルスキルに対する自信がついた者は約半数であった。本介入プログラムにおいて、「デジタルスキルに自信がついた」と答える参加者の割合が70%に満たなかったのは、元々スマホを所有していない参加者が一定数いたことから、デジタルスキルの学習内容をあまり高く設定していなかったことが一因かもしれない。元々スマホを所有していた参加者にとっては既知の内容となり新たなスキルの習得にはならなかった可能性がある。参加者全体の効果として目標の70%に到達できなかったが、一部の特性を持った参加者では70%以上の結果を得られた。こうしたことから、集団での介入に加え、個人にテーラーメイドされた介入の必要性も見出された。
成果目標 5)コミュニティー参加後に幸福度/生活の質が改善したと60%が報告
教室型コミュニティー介入では、幸福度/生活の質の改善に対しても評価を実施した。「幸福度が改善した」と報告した参加者は611名のうち540名(88.4%)であり、「生活の質が改善した」と報告した参加者は611名のうち496名(81.2%)であった。男女別にみると、どちらの評価においても、男性より女性の方が「改善した」と報告する割合が高かった。教室型コミュニティーの参加者からは「新鮮で楽しくできた」、「アプリを理解することができた」、「さまざまな人との交流の機会になった」といったポジティブな声を多く得ることができた。また、一定スキルを有した参加者がスマホの利用が苦手な参加者に使用方法を教えるといったコミュニティー内のつながりが強固され、教える側と教えられる側の交流の機会を促進し、役割を創出することにつながった。出会いと交流の促進、そして役割の創出ができたことから、幸福度や生活の質の改善はともに80%を超える結果になったと考えられる。
課題と対策
自治体と連携し、デジタルヘルス推進員を養成し、高齢者に通いの場アプリを通してデジタルスキルを学習してもらった。適切な目標設定やインセンティブを付与することで、継続的にデジタルとつながりを持ち続けることができる可能性を見出した。しかし、費用のかかるインセンティブは、それを捻出する団体にとって負担となり、継続性に難がある。また目標設定を行うにも個人を理解しているスタッフ等の人材の存在や周囲とのつながりがなければ、目標達成に向けた個人の行動変容は起きづらいかもしれない。
さらに、本プロジェクトを通して如実に現れたのが、高齢者の多くが自身の知らないことに対する恐怖心や不安が多く、学習した以上のことを実施しないということであった。特に、女性や後期高齢者にその傾向が強かった。スマホ等のデジタルデバイスの操作方法を学ぶことはもちろんだが、デジタルの危険性と有効性についても学び、デジタルリテラシーの向上を同時に図ることの重要性が明らかとなった。一方、高齢者であっても正しい知識、正しい技術を提供することにより、それらを有効に活用することが可能であることも明らかとなった。
スキルを教えるといった役割の創出により、個人の生きがい形成につながり、そして、教えられる側が教える側に成長するといった構図も確認することができた。さらにはコミュニティーに参加しデジタルスキルを学習し続けたことにより、対面でのつながりだけでなく通いの場アプリを通した非対面でのつながりの形成にもつながった。
謝辞
本プロジェクトは、 Googleの慈善事業部門であるGoogle.orgおよび、公益財団法人長寿科学振興財団による「高齢社会課題解決研究および社会実装活動への助成」(研究代表者:島田裕之)を受けて実施した。
文献
- (2025年3月24日閲覧)
- (2025年3月24日閲覧)
- (2025年3月24日閲覧)
- 片山脩, 島田裕之: 高齢者に対する「オンライン通いの場アプリ」. 精神医学 2025; 67(1): 89-95.
筆者

- 島田 裕之(しまだ ひろゆき)
- 国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センターセンター長
- 略歴
- 2003年:北里大学大学院医療系研究科臨床医学リハビリテーション医学専攻博士課程修了、東京都老人総合研究所研究員、2005年:Prince of Wales医学研究所客員研究員、2006年:東京都老人総合研究所研究員、2010年:国立長寿医療研究センター室長、2010年:名古屋大学大学院医学系研究科客員研究員(現在兼任)、2014年:国立長寿医療研究センター予防老年学研究部長(現職)、2015年:名古屋大学未来社会創造機構客員教授、信州大学医学部特任教授(現在兼任)、2019年:国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センターセンター長(現職)、2019年:同志社大学客員教授(現在兼任)、2023年:理化学研究所客員研究員(現在兼任)、2024年:東京都立大学客員教授(現在兼任)
- 専門分野
- リハビリテーション医学、老年学
- 過去の掲載記事
- 山口 亨、山際大樹、赤井田将真、片山 脩
- 国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部
WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート
WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。
お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。