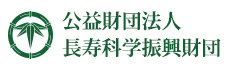医療が大きく変わるとき(長谷川敏彦)
公開日:2025年4月10日 15時29分
更新日:2025年4月10日 15時44分
こちらの記事は下記より転載しました。
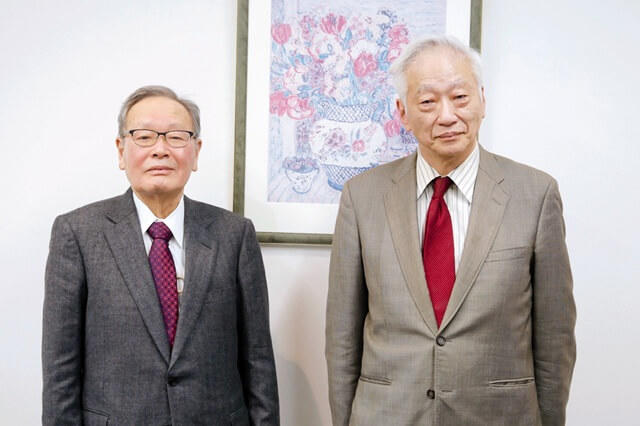
シリーズ第13回長生きを喜べる社会、生きがいある人生をめざして
人生100年時代を迎え、一人ひとりが生きがいを持って暮らし、長生きを喜べる社会の実現に向けて、どのようなことが重要であるかを考える、「長生きを喜べる社会、生きがいある人生をめざして」と題した、各界のキーパーソンと大島伸一・公益財団法人長寿科学振興財団理事長の対談の第13回は、一般社団法人未来医療研究機構代表理事の長谷川敏彦氏をお招きしました。
医療は社会の産物で大きく変わる
大島:長谷川さんを一言で言えば、非常に"個性的な人"ですが、私にとっては非常に価値ある存在です。私は名古屋大学の泌尿器科の教授として当時は移植医療に携わっていました。病院長になって病院経営を考えなければならなくなり、自分のカバーする範囲が少しずつ広がっていきました。国立長寿医療センターの総長に赴任してからは、日本の高齢者医療をどうするのかが最大の課題になりました。守備範囲が広がっていけばいくほど、長谷川さんは私にとって欠くことのできない存在だと強く感じ、これまでお付き合いをさせていただいています。
超高齢社会を迎え、医療の変化がはっきり見えてきました。日本の医療がこれからどのように進んでいくかについて、お話をいただきたいと思います。
長谷川:総長になられて私に研究の依頼をされました。「長寿医療とは何か」「高齢者医療はどういうものだろう」「何が課題か」と問われるのが普通の考えでしょうが、大島先生はその時、「高齢社会はどういう社会なんだろう」と疑問を投げかけられました。医学界の権威にはめずらしく、医療は社会の産物といったお考えでした。
おそらく大島先生の中で、「高齢社会で医療はどういう形をとればよいのか。その医療はどうあるべきか」という順番に考えておられたのだと思い、大変驚き、尊敬いたしました。
3年ぐらい前に門田守人先生(元日本医学会会長)に頼まれて、日本医学会で120年後の医療を考える委員会の委員をやりました。門田先生と大島先生は大きな展望から医療を捉えるちょうど双璧を成しています。日本の医学界をリードし、とにかく病気を治すことに邁進し、そのための理論と技術を磨くことに生涯を費やしてきたような人で、医学医療の意味を捉え直してきた人は少ないので、お二人は日本にとって貴重な人材です。門田先生はお亡くなりになり、大変残念です。
超少子超高齢デジタル社会に向け、専門家だけではなく多くの人にも医療のあり方を考えてもらう必要が広がってきていると思うのです。その対話には先生のような方が必要です。人口、技術変化によって社会全体の構造がドラスティックにこれから変わっていく今、大島先生がおっしゃったように「医療は社会の産物」であるとすれば、社会も医療もすごく変わります。
大島:国立長寿医療センターの総長に赴任した当初、自分は何をすべきかわからず、長寿医療や高齢者医療について手探りでした。模索する中で、自分の中で少しずつ方向性が見えてきたとき、いろいろな影響を受けた方が何人かいますが、長谷川さんはその一人です。
当時、医学教育では学問と技術についてきちんと体系化されていましたが、高齢社会に入り、「医療は治すことだけが目的ではない」ということを突きつけられ、「年を取れば老いる」ということに正面から向き合うことなくして、人が老い死ぬということに医療がどうすべきかは見えてこないでしょう。
医学判断学と問題解決型の手法
長谷川:高齢者のための医療がきちんと教えられていないと、よく医学教育が批判されます。しかし事態は二重の意味で深刻です。まだ高齢社会に対応した新医学大系が成立していないので、何を教えていいかわからない。やっと大島先生を中心に教科書づくりが始まりましたが、これからです。もう一つの課題は、高い授業料を払っているのに、医学校では「医師とは何をする職業か」という根本的な課題が教えられていないことです。教える方も医科学者なので、医療は「疾病の存在を科学的に証明すること」と誤解されがちです。クライアント(患者)が持ち込んだ問題が医療の課題かどうかを他の専門家とともに技術を用いて判断し、根拠に基づく解決法(治療)をケア(医療)チームをリードして提供し評価すること。このプロセスとサイクルこそが医療なのです。私がハーバード大学で学んだ医学判断学を基にしています。これが理解されればケアサイクルにも応用されます。

大島:その頃、日本医学教育学会では問題解決型の手法(POS:Problem Oriented System)に力を入れていましたね。学会主催で、それぞれの全国の病院の管理者クラスを呼んでワークショップも開催していましたが、なかなか広がっていきませんでした。
長谷川:それは、教育を提供する科学者としての医学界の文化に合わなかったからです。真理を追究する科学者が実際に患者さんと向き合って問題解決を支援する方法を教えることが難しかったのです。同時に、高齢社会の進展に伴い、医療自体が大きく転換される必要があり、医療政策も変化し始めています。にもかかわらず、医学界はそれにキャッチアップできていないのが現状です。
生涯を追う第4世代の公衆衛生
大島:現在では、患者はある疾患を何年かかけて悪化・回復を繰り返し、徐々に終末に向かっていくというプロセスの中で、生きることを支援するという視点が重視されています。この状況において、公衆衛生とは何かを改めて考える必要があります。
長谷川:公衆衛生は、集団を対象とする学問体系です。臨床は一対一の関係で問題解決するのですが、公衆衛生では集団全体、つまり社会全体で解決策を模索します。したがって、統計的な分析に基づく疫学が中心にあります。
1980年代は分析疫学といって、疾患の原因を追究するのが目的で記述疫学に続く第2世代の疫学と言われていました。ところが、1980年代から90年に私がハーバードに行く前後ぐらいから第3世代が登場し、治療法、つまり臨床医学そのものを対象にし、科学的根拠に基づく医療「EBM(エビデンス・ベースド・メディスン)」が提唱されました。現在はもう一歩進んだ第4世代で、生涯を通じて個人の健康を追っていくという生涯疫学(ライフコースアプローチ)が広がっています。
大島:日本医学教育学会は盛んにEBMを進めようとしていましたね。ですが、臨床学会への影響力がどれほどなのかはわかりません。EBMという言葉自体は広く知られていますが、重要なのは、「個別だけではなく全体」を見ることだと思います。日本の公衆衛生について、長谷川さんはどうお考えですか。
長谷川:前述のように公衆衛生学がいよいよ重要になっていると思うのですが、どうも存在感が薄い。昔の世界に安住している。しかし一方で、新たに日本でも加齢による病気の発生を生涯かけて見ていく取り組みが始まっています。その代表例が元JAGES代表理事で千葉大学特任教授の近藤克則さんです。もう一つ重要なのは、ヘルスポリシー(医療政策)の分野への応用です。行政が医療政策を展開し、その効果を評価するには公衆衛生の手法が必要ですが、残念ながら日本では十分に成熟していません。
進歩をコントロールする知恵は
大島:科学は進歩し、社会も変わり続けています。これは止めようがありません。それに伴い、人間のライフスパン、生涯というものも当然変化せざるを得えません。子どもから成長して大人になり、老人になって死を迎える。そのことだけは変わらないけれども、置かれている環境自体は常に変化します。そういう中で医療がどう対応してきたのか。そして今後、変化の渦中でどう対応していくべきでしょうか。
長谷川:進歩と言われますが、本当にそうなのでしょうか。確かに物質的に人類は様々な手法で、大きな物質を動かせるようになりましたが、それが幸せにつながっているのか。
大島:もちろん利便性を高めるという意味での進歩と意味は違いますよね。
長谷川:人類は多くの手段を手に入れ、利便性を高め、食糧を増産し、結果的に人口を増やしてきました。しかし、それは本当に進歩と言えるか疑問です。生産性が高まることによって、自然を圧迫して、環境破壊が起きています。今では無生物から生物をつくれると称する科学者も出てきました。10万円ぐらいの機器でDNA操作ができ、どんどん新しい生物をつくることもできます。また、ITに関して言えば、AIやVRが進化して経験したことのない世界が広がっています。しかし、人類はこうした技術をコントロールする能力は十分にありません。
技術にはプラスとマイナスの面があります。その使い方を適切にコントロールして、われわれが生きていくために必要な技術として活用する知恵が備わっているのかが問われています。

近代医学の要素還元主義では見えないもの
長谷川:近代医学はだいたい1860年ぐらい、まさしく170年前のクリミア戦争の頃にでき上がりました。それより前、フランスやドイツで、「要素還元的特定病因論」の考え方が進み、病気の原因をできるだけ小さく身体の部分で捉えようとしました。最初のフランスでは肉眼で捉えた病理学、フランス革命後、解剖が許可されて剖検ができるようになったからです。さらに細胞レベルで疾病を定義しようと、1850年頃にドイツでレンズの解像度が上がり、化学染料ができ、原因を小さな細胞単位で把握するようになり、医学の爆発的な発展がありました。
近代医学はデカルトの考え方に基づき、身体を機械のように捉え、病気を局所の損傷と定義してきました。そして、研究対象は徐々に細分化され、最終的に細胞レベルまで達しました。しかし、心の病については局所の細胞の異常だけでは説明がつかず、近代医学にとって最大の課題となっています。
そして今、高齢化が進み、近代医学の目的が病気の治癒や救命から身体機能やADLの改善、さらにQOL・QODの向上に転換してきました。高齢者のみならず、中年のうつ病、子どもの発達障害など心の課題がクローズアップされています。
大島:精神状態がある行動に結びつくということは現実にあります。ある精神疾患が似たような行動に結びつくというようなエビデンスもあります。それが物質なのか、何か他の要因なのかというようなことについて、証明のしようがありません。ただ、いわゆるサイエンスを信奉する考え方では、「必ず原因があるはずで、原因はきちんと目に見えるはずだし、物に還元されるはずだ」と叩き込まれています。
長谷川:極論を言えば、サイエンスと言われる体系は、「再現性を追求して説明をする」という、ある種の宗教ですね。
大島:確かに、その通りですね。
長谷川:たぶんこれが今、変わるべきターニングポイントです。
大島:この60、70年の間に劇的に変化しました。今後さらに大きな変化が起こることはもう間違いありません。私はまだ若い頃、医師として身体しか見ていませんでした。そこに何の矛盾も感じなかったし、サイエンスというのはそういうものだと叩き込まれ信じてきました。1分1秒でも長生きさせるという目的もはっきりしていたし、医師としての技術を磨きに磨いて、間違いのない技術を投入することによって病気の完治や延命が可能なのだと思っていました。しかし、老いや死に直面すると、それだけではとても対応はできないし、医療としての限界も見えてくるということがわかってきました。
長谷川:私が外科のレジデントを終えた後ハーバード大学に公衆衛生を学びに行った動機の一つに、1976年当時に出版されたイギリスの疫学者トーマス・マッキューン教授による『医学の役割』という本があります。それには、西洋近代医学は死亡率の低下にほとんど貢献してこなかったと書かれていたからです。19世紀の半ばまで西洋では「体液説」に基づく伝統医学が使われており、コレラのパンデミックで瀉血(しゃけつ)が使われ、たくさんの患者が治療によって亡くなりました。その反省のもとに新たな近代医学が成立したのですが、今まったく同じ状況ではないでしょうか。ケアサイクルに入った高齢者に暮らしの中のケアが必要なのに、病院での治療が中心となっている。残念ながらまだ新しい医学の体系が成立しておらず、19世紀のドイツのように、人類のために新医学を確立することが21世紀の日本の使命です。
大島:話がどんどん広がっていきますが、次号ではさらに医療のあり方について話していきましょう。今日はありがとうございました。
対談者

- 長谷川 敏彦(はせがわ としひこ)
- 一般社団法人未来医療研究機構代表理事
1948年生まれ。大阪大学医学部医学進学課程卒業。外科医として3年つとめた後、アメリカ・聖ヨセフ病院で専門医となり、ハーバード大学公衆衛生修士課程卒業。滋賀医大を経て、国立がんセンター企画室長、厚生省・老人保健課課長補佐、JICA(国際協力機構)課長、九州医務局次長、国立医療・病院管理研究所(後に国立保健医療科学院)医療政策研究部長、日本医科大学医療管理学教室教授を歴任。2025年より帝京科学大学教授。主著に『超少子・超高齢社会の日本が未来を開く』(集英社)などがある。

- 大島 伸一(おおしま しんいち)
- 公益財団法人長寿科学振興財団理事長
1945年生まれ。1970年名古屋大学医学部卒業、社会保険中京病院泌尿器科、1992年同病院副院長、1997年名古屋大学医学部泌尿器科学講座教授、2002年同附属病院病院長、2004年国立長寿医療センター初代総長、2010 年独立行政法人国立長寿医療研究センター理事長・総長、2014年同センター名誉総長。2015年認定介護福祉士認証・認定機構理事長(現・機構長)。2020年より長寿科学振興財団理事長。2023年瑞宝重光章受章。
WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート
WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。
お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。