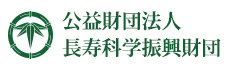楽しみながらポイントをためて健康になる〜山形市健康ポイント事業SUKSK〜(山形県山形市)
公開日:2025年4月10日 12時59分
更新日:2025年4月10日 14時08分
こちらの記事は下記より転載しました。
SUKSK生活で健康寿命延伸を目指す
山形県山形市は「健康医療先進都市」をビジョンに掲げ、2019年より健康寿命延伸を目指す「SUKSK(スクスク)プロジェクト」を推進している。健康寿命を損なう三大原因を「認知症」「運動器疾患」「脳血管疾患」と分析し、これらの発症を抑えるには生活習慣病の予防が重要と考え、食事(S)、運動(U)、休養(K)、社会参加(S)、禁煙・受動喫煙防止(K)に留意する「SUKSK生活」を提唱している。
プロジェクトの中心となるのが、「」(以下、ポイント事業)である。市民が楽しみながらポイントをため、健康意識を高めることを目的としている。専用のスマホアプリ(以下、SUKSKアプリ)や歩数計などを活用し、歩数計測、健康イベントへの参加などでポイントを獲得。一定のポイントで抽選に参加でき、当選者に県内の特産品などが当たるという仕組み。
ポイント事業には、市民のほか、登録事業所に在勤している人も参加できる。登録者数は年々伸びており、事業開始時の2019年には約3,200人だったが、2025年2月には1万7,000人を突破し、約5倍に増加した。市の人口約24万8,000人のうち6%超がこの事業に参加しており、「SUKSK生活」が市民に浸透しつつあることがうかがえる。SUKSKプロジェクトは、2023年に「」において厚生労働大臣最優秀賞を受賞し、全国的にも注目される取り組みである。
エビデンスに基づく健康医療政策
プロジェクト推進の背景には、2019年の中核市への移行がある。中核市となったことで市は保健所を設置できるようになり、保健所長には原則として医師が就任する。行政に近い立場に医師が着任したことで、エビデンスに基づいた健康医療政策の推進が可能となった。市民の健康情報を分析した結果、健康寿命延伸には、食事、運動、休養、社会参加、禁煙・受動喫煙防止の5つの要素がカギであることが明らかになり、「SUKSK」のキーワードが生まれたという。

(出典:
山形市健康医療部健康増進課長の後藤好邦さんは、「保健所と健康医療部を一体化し、健康医療政策を進めています。保健所は一般的な保健所業務のほか、健康医療政策の頭脳となり、政策に反映させる分析を行っているのが特徴です」と話す。健康医療部は山形市保健所内に設置され、両者が連携しながら健康医療政策を進めている。
歩く・食べる・楽しむー多彩なポイント対象事業
ポイント事業への参加方法には、SUKSKアプリ、歩数計、介護予防手帳がある。参加者の9割が使用するSUKSKアプリは、ドコモの汎用型アプリを市の事業に合わせて使用。アプリの特徴としては、歩数計測のほか、二次元バーコードの読み込みによりポイントを提供できる点にある。
ウォーキングでは「8,000歩以上で100ポイント」など、一日の歩数に応じてポイントが付与される。健診・検診の受診、健康イベントへの参加、低山ハイキング、「モンテディオ山形」の観戦、花笠まつりへの参加、地域活動など、250以上のポイント対象事業がある。介護予防手帳による参加者には、通いの場で開催される「いきいき百歳体操」などでもポイントが付与される。
身体活動に加え、栄養面においてもポイントが付与される仕組みも興味深い。市内24店舗の飲食店で提供される市認定の「SUKSKメニュー」には、「栄養バランス」「食塩控えめ」「野菜たっぷり」の3つの基準があり、すべての基準を満たしたメニューは「SUKSK三ツ星」となる。
山形市はラーメン消費日本一のまちとして知られている。「ラーメンのまちというブランドを生かしつつ、ラーメンとともに野菜も一緒にとると、よりバランスのとれた食事になりますという提案もできます」と健康医療部健康増進課SUKSK推進係長の大場俊幸さんは語る。
新たなポイント対象事業の導入で参加者のモチベーション向上
参加者の心を捉える事業を次々と展開している。毎月第3土曜・日曜の「ポイントアップデー」には、8,000歩以上でSUKSKポイントが5倍になる。該当日には8,000歩以上歩く参加者が3割を超え、年間平均を大きく上回った。「ポイントアップはアプリ限定の特典です。デジタルの特性を生かした仕組みを導入することで、歩数計や介護予防手帳からアプリへ移行を促すきっかけにもなります」と大場さんは語る。
健康分野の専門家を「SUKSKマイスター」として委嘱し、「SUKSKスクール」を開講している。フィットネストレーナーの中沢智治氏とフットヘルパーの大場マッキー広美氏が講師を務め、市民は楽しく体を動かしながらポイントを獲得できる。さらに、楽天グループとの連携による「楽天50万ポイント山分けキャンペーン」など、参加者を飽きさせない工夫が充実している。

抽選会は年2回開催される。5,000ポイントを1口として抽選に参加でき、山形牛などの山形の特産品、地域で使える商品券などが約3,500名に当たる。後期の抽選では10口(5万ポイント)まで応募が可能で、ポイントが多いほど当選確率が上がるため、参加者のモチベーション向上にもつながる。
健康リテラシー向上と健康寿命延伸への効果
ポイント事業の登録者数は2025年2月時点で約1万7,000人。年平均44%のペースで増加している。登録者の約3割は登録事業所からの参加者である。年代別では40代、50代、30代の順で多く、約7割が現役世代である。「健康寿命を延ばすには、働き盛り世代へのアプローチが重要です。若いうちから健康を意識することで、10年後、20年後に効果が表れます。そのため30〜50代をコアターゲットにしています」と後藤さんは話す。
2023年に実施したSUKSKアプリ利用者のアンケートでは、「健康への意識変化が高まった」「行動変容につながった」と答えた人が約9割という結果だった。「単に歩数のカウントでなく生活のバロメーターになっているとか、ポイントをためて抽選に参加するということを超えて、健康づくりのツールになっているという話を聞きます」とSUKSK推進係主任保健師の小林桜子さんは語る。
健康データにも効果が表れ始めている。2013年と2022年の比較では、男性の平均寿命は81.17歳から81.95歳に、健康寿命は79.84歳から80.70歳に延伸した。女性の平均寿命は87.44歳から87.97歳に、健康寿命は84.46歳から85.07歳に延伸。平均寿命と健康寿命の差である「不健康期間」は、男性で1.33歳から1.25歳に、女性で2.98歳から2.90歳に短縮された。
また、介護保険1号被保険者(65歳以上の高齢者)は増えているものの、要介護2以上の認定者割合は2018年度の10.1%から2023年度には9.3%に減少。三大原因(認知症、運動器疾患、脳血管疾患)による要介護2以上の認定者割合も、2018年度の71.5%から2023年度には66%に低下し、特に認知症による要介護2以上の認定割合が減少している。こうした成果を発信するため、山形市では」を2025年3月に開設した。

AI健康アドバイスで個別最適アプローチを実現
SUKSKアプリの新機能として、2025年2月から「」を開始した。健診結果とアプリの歩数データをもとに、AIが血糖値と中性脂肪の上昇リスクを分析し、改善に向けたミッションを毎週スマホに配信。ミッション達成でポイントが獲得できるという仕組み。これまでの「皆で歩いて健康になろう」という全体最適のアプローチから、一歩踏み込んだ個別最適のアプローチを進めている。
AI健康アドバイス導入の背景には、要介護2以上の原因疾患において、女性では運動器疾患に改善が見られないこと、男性では悪性腫瘍が増加していることがある。他にも、急性心筋梗塞が男女ともに全国平均より高く、プロジェクトの効果が表れている一方で、課題も残されているという。
「これらの課題に対応するため、心筋梗塞や悪性腫瘍などの危険因子を持つ方への個別最適のアプロ--チが大事になると考えます」と後藤さんは語る。
AI健康アドバイスでは、利用者の承諾を得たうえで、マイナポータルから健診データを自動取得できる。健診データとSUKSKのデータを統合し、AIが解析する仕組みは全国初の試みである。
デジタル技術を効果的に活用し、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの二本柱で市民の健康を守る。進化しつづけるSUKSKプロジェクトは全国自治体の健康医療政策のモデルケースとなるだろう。
WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート
WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。
お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。