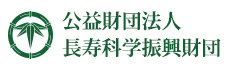第1回 心理学者の認知症研究事始め
公開日:2025年4月11日 10時30分
更新日:2025年4月11日 10時30分
こちらの記事は下記より転載しました。
佐藤 眞一
大阪大学名誉教授、社会福祉法人大阪府社会福祉事業団特別顧問
医学者でも社会福祉学者でもない心理学者である私が認知症の研究をしていることを不思議に思われていた時代がある。
しかし、今や書店に行けば認知症の人のこころをテーマにした一般向け書籍がたくさん並んでいる。それらの書籍の中に私の書いたものも何冊か混じっているのを見ると、心理学者として認知症研究を続けてきたことは、おそらく間違いではなかったのだろうと思う。
また、2023年6月に公布された「認知症基本法(略称)」が、昨年、2024年1月に施行され、「新しい認知症観」を強調する基本計画が同年12月に閣議決定された。従来の否定的な人間観を内包する「古い認知症観」を、認知症の人も地域で共に暮らす意志と権利を有する個人として、そのこころの中も含めて他者が理解していくことの必要性が強調されている。「我が意を得たり」の気持ちで一杯になったことを思い出す。
私の大学入学の少し前に東京都老人総合研究所(以下、都老研、現・東京都健康長寿医療センター研究所)が設立され、心理・精神医学部に大学の先輩が所属していた。また、大学院博士後期課程に老年心理学を始めたばかりの先輩もいた。その先輩方の研究会に参加させてもらえることになり、私は大学1年生の終わりには大学院に進学して老年心理学の研究者になることを決めていた。
高齢者施設の現場に出てみると、当時は脳血管障害の後遺症で身体麻痺や失語症、さらには脳血管性痴呆のある利用者が多く、コミュケーションの難しさに苦労している介護職員の多いことを知ることになった。同時に、介護職員は、当時はまだ少なかった老年痴呆の原因不明でしかも理解不能な言動に困窮していることも知るようになった(「老年痴呆」は、アルツハイマー病を含む神経変性が原因の認知症疾患の当時の総称)。
都老研に研究員として所属していた頃に、ロンドン大学の二人の心理学者、エドガー・ミラーとロビン・モリスの著書 『The Psychology of Dementia』(1993年刊)に出遭った。日本に類書がなかったため、私は痴呆の心理学の全般を学ぼうと本書を読み始めた。そして、その序論にあった以下の言葉に私はいきなり大きな感銘を受けた。後に私が翻訳出版した時の訳でその言葉を示したい1)。
「痴呆という問題への関心は、近年、かなり広まってきています・・・(中略)・・・。それにもかかわらず、まさに『痴呆』という言葉は、何よりも痴呆が知的機能の低下を意味するという点で、第1に心理学的なものなのです。」
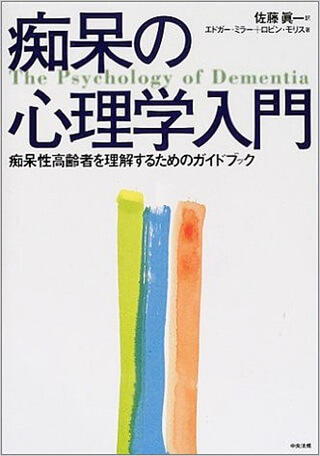
知的機能の研究は、学術的には発達心理学と教育心理学から始まっていて、すでに成人や高齢者の研究も進んできていた。正常発達から逸脱した知的機能の人が「痴呆」と呼ばれていることを改めて思い返した私は、ならば心理学者として痴呆を本格的に研究しようと考えたのである。
すでに都老研から私立大学に転職していた自由さから、私は手当たり次第に痴呆の人やその介護者を対象に実験や調査を始めた。
一例を示そう。認知機能(知的機能)は、それぞれの人のこころの中のことではあるが、行動上で他者に示される現象でもある。しかし、痴呆症の人と介護者の関わりの中で事実と認識の間にすれ違いが起こっていないかと考えた私は、次のような研究を大学院生と共に行った。
認知機能を評価する検査を数種類用意して痴呆症の本人に実施し、それとは別に介護職員に検査を受ける痴呆症のそれぞれの人が各課題に正解できるかどうかを尋ねた。両者の結果は私たちに予想以上の問題を示唆していた。認知機能課題のうち、特に、当時は痴呆の評価基準に必須であった記憶課題に関して、介護職員が正解できないと答えた設問に、痴呆症の対象者が正解できた事例が多数あり、統計的に有意に介護職員が痴呆の人の記憶能力を実際よりも低く評価していることが明らかになったのである2)。
介護職員が、痴呆症の利用者の記憶能力を実際よりも低く評価していたのはなぜか、そのことと介護業務との関連性はないか、実際の能力よりも知的に劣っていると思われて介護されている利用者は何をどう感じているのか、それが行動上に現れていないか、介護がうまくいかない要素の一つになっていないか、等々この結果から考えなければならないことが次々に湧いてきた。
当時はまだ痴呆といわれていた認知症の人への「古い認知症観」が、この研究結果から透けて見えるようである。
文献
- エドガー・ミラー, ロビン・モリス著, 佐藤眞一訳, 痴呆の心理学入門. 中央法規出版, 2001.
- 川口裕見, 佐藤眞一, 痴呆性高齢者の認知能力の他者評価に関する研究. 高齢者のケアと行動科学 2002;8(2): 37-45.
著者

- 佐藤 眞一(さとう しんいち)
- 早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(医学)。東京都老人総合研究所研究員、マックスプランク人口学研究所上級客員研究員、明治学院大学心理学部教授、大阪大学大学院人間科学研究科教授などを経て、現在、大阪大学名誉教授、社会福祉法人大阪府社会福祉事業団特別顧問。専門は老年心理学、老年行動学。『心理老年学と臨床死生学』(ミネルヴァ書房)、『老いのこころ--加齢と成熟の発達心理学』(有斐閣)、『認知症の人の心の中はどうなっているのか?』(光文社)、『心理学で支える認知症の理論と臨床実践』(誠信書房)など著書多数。
WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート
WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。
お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。