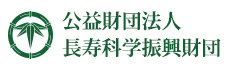ロコモティブシンドロームの診断
公開日:2016年7月25日 13時00分
更新日:2024年2月 8日 10時20分
ロコチェック
ロコチェックとは、骨や筋肉、関節などの運動器が衰えていないかを7つの項目でチェックできる簡易テストです。7項目のうち、ひとつでも当てはまればロコモティブシンドロームの心配があります。
チェック項目は以下の7つです。
1.片脚立ちで靴下がはけない

2.家の中でつまずいたりすべったりする

3.階段を上るのに手すりが必要である

4.家のやや重い仕事が困難である

5.2kg程度(1Lの牛乳パック2個程度)の買い物をして持ち帰るのが困難である

6.15分くらい続けて歩くことができない

7.横断歩道を青信号で渡り切れない

7つの項目のうち、1つでも当てはまる項目があれば、運動器が衰えているサインです・ロコモティブシンドロームの心配がありますので、当てはまる項目がゼロとなるように、ロコモーショントレーニング(ロコトレ)※を行いましょう。
膝・腰などの関節の痛みや、筋力の低下、立ち上がる時や歩く時にふらつくなどの症状がひどくなってきている場合は、整形外科を受診するようにしましょう。
- ※ ロコモーショントレーニング(ロコトレ):
- ロコモーショントレーニング、通称「ロコトレ」とは、2種類のトレーニングで「バランス能力」と「下肢の筋力」を改善することのできるトレーニング方法のこと。
ロコモ問診票
ロコチェックの内容を「はい」、「いいえ」でチェックし、項目によって、さらにその理由や、詳しい内容、状態、痛みの出る部位などを細かくチェックできるようになっています。医療機関への受診の際に持参すると、医師に運動機能や生活面での詳しい状態を伝えることができます2)。
ロコモ度テスト
「立ち上がりテスト」、「2ステップテスト」、「ロコモ25」の3つのテストから移動機能の状態を確認できるテストです。
立ち上がりテスト
下肢の筋力を調べるテストです。両脚、または片脚で10~40cmの台から立ち上がられるかをテストします。
両脚の場合(図1)
- 10cm、20cm、30cm、40cmの台を用意します。
- 40cmの台に座り、足は肩幅に開いて少し後ろに引きます。(脛の角度が70度になるようにします。)
- 反動をつけずに立ち上がり、そのまま3秒間止まります。
- 40cmの台から立ち上がることができたら、片脚テストを行います。

片脚の場合(図2)
- 40cmの台から両脚で立ち上がることができたら、40cmの台に両脚テストのときと同じように座って、膝を軽く曲げて片脚を上げます。
- 片脚を上げたまま、反動をつけずに立ち上がり、3秒間止まります。

2(ツー)ステップテストの方法
歩幅を測定して、下肢の筋力やバランス能力、柔軟性などを含めた歩行能力を総合的に評価することができます(図3)。
- スタートラインを決め、両足のつま先を合わせます。
- できる限り大股で2歩歩き、両足を揃えます。(バランスをくずした場合は失敗とします。)
- 2歩分の歩幅(最初に立ったラインから、着地点のつま先まで)を測ります。
- 2回行って、良かったほうの記録を採用します。
- 次の計算式で2(ツー)ステップ値を算出します。

ロコモ25
1か月間に身体の痛みや日常生活で困難なことがあったかを25項目の質問でチェックします。5段階で答えるようになっています(図4)。

ロコモ度判定方法
ロコモ度テストの結果から「ロコモ度1」または、「ロコモ度2」を判定します。
ロコモ度1の判定内容
- 「立ち上がりテスト」で、どちらか一方の片脚で40センチの高さから立ち上がれない。
- 「2ステップテスト」で、2ステップ値が1.3未満
- 「ロコモ25」で、結果が7点以上
のいずれか一つでも当てはまる場合(図5)
ロコモ度1の場合は、筋力やバランス能力の低下がみられ、移動機能が低下してきている状態です。

ロコモ度2の判定内容
- 「立ち上がりテスト」で、両脚で20cmの高さから立ち上がれない
- 「2ステップテスト」で、2ステップ値が1.1未満
- 「ロコモ25」で、ロコモ25の結果が16点以上
のいずれか一つでも当てはまる場合(図6)
ロコモ度2の場合は、移動機能が低下し、日常生活に支援や介助が必要となってくるリスクが高い状態です。特に痛みがある場合は、運動器の疾患を伴っていることもあるので整形外科を受診しましょう。

ロコモティブシンドロームの診断の流れ
ロコモティブシンドロームの診断は、普段の生活を振り返って7つの項目をチェックするだけの「ロコチェック」と、立ち上がりテスト、2(ツー)ステップテストの運動機能テストを実際に行い、25項目の質問に答える「ロコモ度テスト」の2通りの診断方法があります。
どちらもロコモティブシンドロームの心配があるという結果になった場合はロコトレを実施し、ロコモティブシンドロームの改善を図ります。
「ロコチェック」で痛みを生じる場合、運動器の衰えに不安を感じている場合、「ロコモ度テスト」でロコモ度2であった場合は、整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう。
運動器の機能は、加齢や環境の変化などの影響を受けるため、定期的にチェックを行って自分の状態を客観的に捉え、気になる症状があった場合は早めに受診して対策できるようにしましょう(図7)。