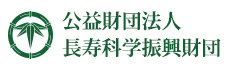第1回 移動困窮社会にならないために
公開日:2025年4月11日 10時30分
更新日:2025年4月15日 11時01分
こちらの記事は下記より転載しました。
鎌田 実
東京大学名誉教授、一般財団法人日本自動車研究所所長
少子高齢化・人口減少の続く日本において、移動の問題が顕著になっていく。公共交通の発達した大都市部以外では、マイカー移動中心の社会であり、街道沿いの大型店舗が栄えている一方、中心市街地はさびれている。高齢運転者が引き起こす事故も社会問題化している。そんな中で、国では、地域公共交通のリ・デザインや共創事業、それから交通空白ゼロに向けての施策を進めており、またドライバー不足によりタクシーが利用しづらい面に対して、日本版ライドシェアの導入なども実施している。
しかしながら、少し遠い将来を考えると、2050年カーボンニュートラルという大きなハードルが控えている。再生可能エネルギーによる電力で動く電気自動車の普及が期待されているが、バッテリーの値段は高く、車の購入・維持にかかる費用が高騰することが予想される。エンジン車でも脱炭素になるような合成燃料の使用もあるが、リーズナブルな価格で必要な量を供給できるかはまだ見通しがきちんと立っているとは言えない。そうなると、今のようなマイカー所有が困難になってくる層が増えてきて、自由に移動ができなくなることが懸念される。筆者はこれを移動困窮社会と呼び、そうならないような手立てを考えて書籍に記した1)。
そこでは、既存のバスとタクシーの間に位置するようなデマンド乗合交通の積極的な活用を期待している。呼べばすぐ来るようなモビリティサービスを十分用意することで、マイカー運転による事故のリスクを回避し、マイカーへ投じていた費用をサービス供給側に提供するようになれば、モビリティサービスの事業性も確保できるのではないかという期待がある。もちろん、呼べばすぐ来るようにするには、それなりの台数が必要で、利用者が多くないと事業としてまわせないし、それだけのドライバー確保もハードルと言えるが、遠い将来にはロボタクシーと呼ばれる無人のタクシーサービスが社会実装されることも期待できるので、そういうところも加味して将来のモビリティ像を描いていく必要がある。
既存のバスは、路線が決まっていて停留所までの距離が遠いとか本数が少なくて不便、またタクシーは利便性が高いが運賃も高く、最近は台数減でつかまりにくくなっている。そこでバスとタクシーの中間的なものとしてデマンド乗合交通があるが、それを今より1桁多い台数を走らせることにより、多くのニーズに応えられるようにしていく、そういうものが当たり前になるような時代を期待したい。
文献
- 鎌田実・宿利正史編著, 移動困窮社会にならないために. 時事通信出版局, 2024
著者
- 鎌田 実(かまた みのる)
- 1987年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。東京大学工学部講師、助教授を経て、2002年東京大学大学院工学系研究科教授、2009年東京大学高齢社会総合研究機構機構長・教授、2013年東京大学大学院新領域創成科学研究科教授。2020年より一般財団法人日本自動車研究所所長。専門は車両工学、人間工学、ジェロントロジー。
WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート
WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。
お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。